 |
正面やや左から全容
13.8(W)x10.5(H)x16(D)cm とコンパクト
重量は、2340g 軽量感はありません!
むしろ頑強なイメージです |
 |
リアパネルの様子です
アンテナは、M-R
DC電源は一般的なジャックです
ヒューズも標準のφ6.4x30mmのもの
左から
サイドトーン音量調整、MIC入力、MICゲイン調整、CWパワー(指でつかめます)、パドル接続(エレキ―内臓)、キー接続 |
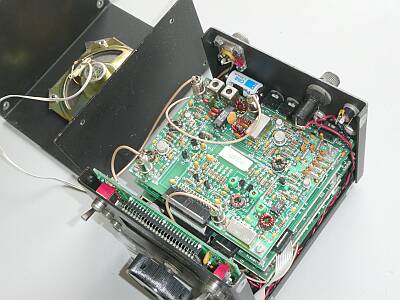 |
上蓋を開けて上から見た中身です
スピーカーは天板に取り付けられています
アナログVFOなら音声出力でドリフトしそうですが、さすがディジタルVFO
バックアップ電池の交換は、当初より上蓋を外すだけでできる構造になっています
|
 |
4層になった基板、上3枚を取り外したところです
フロントパネル裏に、液晶表示部(SW類、ロータリーエンコーダ付き)が取り付いています |
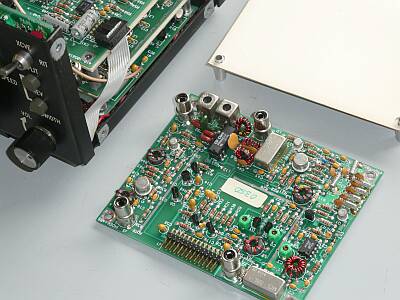 |
一番上に配置されている基板です
後ろに見えているスペーサの上に載せる構造です
受信TOP、ミキサ、クリスタルフィルタ、IFアンプ、プロダクト検波まで
送信については、受信共用のクリスタルフィルタ、ミキサ、そしてプリドライバまで
50〜100mWの送信出力が得られています
いわゆる無線(エキサイタ)部は、この基板1枚です
フィルタは、クリスタル6枚によるもの、基板右奥がそのものです |
 |
AFフィルタ、マイクアンプ、ALC、AGC、AFオーディオなど
バックアップ電池は、オリジナルはCR2016でしたが、長寿命が期待できるCR2に交換しました
電池右上に見えるのが元々ついていた電池ソケット
キー接続端子、パワー調整つまみなど背面に出ている端子、VRは、この基板上に配されています |
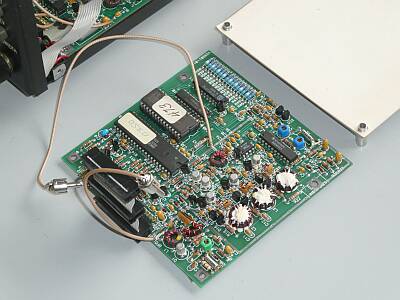 |
コントロール、VCO部です
キャリア(BFO)信号もこの基板で作られています(50MHz一発発信)
今回の不動の原因の一つは、3枚の基板をつなぐフラットケーブルにありました
左端に見えています
この真ん中のコネクタに接続不良がありました |
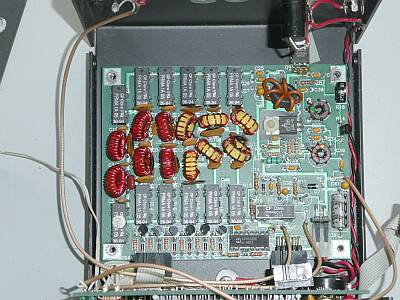 |
ファイナル、LPF部です
4層になっている基板の底部で、ケースに取り付いています
TTL-ICに見えるのは、リード・リレーです
50〜100mWの信号を3〜5Wに増力します
ファイナルは、MosFETで、FHの下、ケースに取り付けられています(放熱都合)
昔流行ったIRF510です
基板上に見えるTrは、ドライバです |