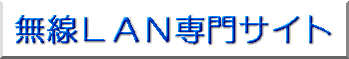| Collins 51S-1 | |||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
| コリンズ製ゼネラル・カバレッジの受信機です 外部スピーカー 312B-3 と並べています セミ・業務向けの受信機として、真空管採用の最後のモデルです 75Aシリーズ(例:75A-2、75A-4)から(軍用では、もっと以前から)の伝統の技術・・・メイン・ダイヤルひとつで、RF段・IF段全てのチューニングを行います、すべてメカニカルです 従って、一般にRFチューニングとか表される同調ツマミはありません 周波数を選択するだけで、最も高感度に受信できる、ということです 昨今の様に、広帯域のBPFを切り替えるような手法ではなく、従来通りの同調を取ります 当然のことながら、高周波段における選択度は高いといえます 1960年初めから1980年代まで生産が続けられたようです 1KHz直読で、2.5〜3.5MHzの1MHzをカバーするPTOと組み合わせ、1MHzごとのバンド切替で、0.2MHzから30MHzを連続カバーします あまりに高名で情報も多いので、ここでは簡単なご紹介にとどめます 数ある受信機の中にあっても、今でも人気の(実力も!)ある受信機です 375W 167H 332D サイズは、KWM-2等と同じで、重量は約11.8Kgあります 0.2〜2MHzは、一度28.2〜30MHzに持ち上げ(アップ・コンバージョン!)、そこから1stIF:3〜2MHzに落とします そこで、PTOの信号(3.5〜2.5MHz)とMixして、500KHzの2ndIFに落とし、検波します 0.2〜2MHzは、トリプル・スーパー・ヘテロダインとなります 2〜7MHzは、一度14.5〜15.5MHzに持ち上げ(やはりアップ・コンバージョン)、そこから1stIF:3〜2MHzに落としますので、この周波数範囲も、トリプル・スーパー・ヘテロダインです 7〜30MHzはダウン・コンバージョン、1stIF:3〜2MHzに一発で落としますので、ダブル・スーパー・ヘテロダインということになります 選択幅を決める500KHzのメカニカル・フィルタについて、collins SLineと聞けば、SSB向けには狭帯域の2.1KHz幅を頭に浮かべそうですが、本機のフィルタは2.75KHz幅で、ダイヤル・カーソルは1本となるようキャリア周波数はひとつで、USBとLSBの2本のフィルタを切り替えます CWは、一般的な仕様では800Hz幅、AMは、IFT(集中IFT)による5KHz幅となっています 本機のCWフィルタは、300Hz幅のものが搭載されています 整流や検波、検波後のSSB/CWオーディオ・プリアンプ、AGCなどには半導体が用いられ、真空管は17球で構成されています RF1段、IF3段増幅という構成です この後は、全体半導体化され周波数表示もディジタル化された、651S-1に選手交代です |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||